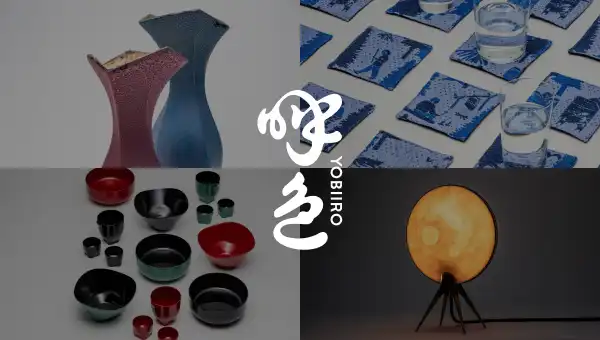1966年山形県寒河江市生まれ。文化服装学院を卒業後、アパレルメーカーに勤務。92年に佐藤繊維に入社し家業を継承、2005年に代表取締役社長に就任。
糸づくりからニットの仕上げに至るすべての工程において「ものづくり」にこだわり、独創的な製品を世界に向けて発信し、付加価値の高い自社ブランドを確立。欧米の一流ブランドに糸を供給するまでに成長し、ニットを消費者に直接訴求する流通を開拓した。
山形県ニット工業組合及び日本ニット工業組合連合会の理事長を務めながら、寒河江市観光物産協会長にも就任し、地域経済の活性化にも取り組む。
ものづくりへの姿勢を、イタリアの展示会で気付かされた
佐藤繊維が創業した経緯を教えてください。
弊社は私の曽祖父が1932年に創業しましたが、紡績工場を作ったのは祖父です。きっかけは、日本の西の方に製糸業の会社があると聞いて、見学に行ったこと。実際に糸を作る現場を見て、感銘を受けたそうです。
ただ、もともと百姓だったこともあり、当時はお金がありませんでした。昔は銀行もお金を貸してくれなかったので、地元の方にお金を借りてのスタート。木を使ったり、古い織り機をバラバラにして組み立て直したりして、必要な機械を作りました。その頃に作った織り機は、今でも弊社の工場に置いてあります。
佐藤さんは、どのような経緯で佐藤繊維に携わるようになったのでしょうか。
私は、ずっとボクシングをやっていました。「世界チャンピオンになろう」とひたすら練習していて、日本ランキング2位までいきました。しかし、自分の才能に限界が見えたためボクシングを辞め、家業に携わる道へと進みました。幼少の頃から、「親の会社をいつか継がなくてはいけない」とは思っていたのです。
文化服装学院を卒業後は、東京でアパレル会社に就職しました。地元に戻ったのは、結婚してからです。私が戻ってきたときには、工場の規模がとても小さくなっている状態でしたね。
そのようななかで、父がニットの機械を7台買ってきました。弊社は機械が買える規模ではなかったので、びっくりしたのを覚えています。当時はハイゲージの機械がトレンドでしたが、購入したのはその一歩手前の古い機械でした。
毎日、夜遅くまでいろいろ試していたところ、7ゲージや12ゲージの糸を混ぜて編むと面白いものが出来上がってきて。そこから、5ゲージ、3ゲージとさらにゲージの低い機械を追加で買って、いろいろな太い糸と混ぜながら編んでいくようになりました。
規模が縮小したなかでも、いろいろな取り組みをしていたのですね。
流れが大きく変わったのは、今から30年ほど前。海外製品が日本へ大量に入ってくるようになったときです。原料である糸の品質は変わらないのに、中国で作ると人件費が日本の20分の1に抑えられますし、染料も安く済むのです。機械の高速化・大型化・自動化が求められましたが、すべてに対応するのは難しいことでした。
転機になったのは、イタリアの展示会に誘われたときのことです。当時、東京で手に取ったセーターがとても面白くて。商社に問い合わせたらイタリアの糸を使っていることが分かったので、その糸を取り寄せました。
そのときにイタリアの会社から、「展示会があるから見に来ない?」と声をかけてもらって。「弊社はイタリアに行くような会社じゃないし…」とは思ったのですが、工場を見に行ったら作り方が分かるので、「このようなチャンスは二度とない」と、思いきって行くことにしました。
「技術を盗もう」という気持ちで工場見学に行ったのですが、工場の方が「これを触ってみろ」「軽いだろ」など、自分たちが作ったものについて熱く説明してくれて。それを聞きながら、私は胸が痛くなりました。「真似をしちゃいけない。やっぱり私たちの工場でものを生み出して、新しい文化を作らないといけない」と思ったからです。
当時はヨーロッパから情報を得て、それと同じものを作るというのが、日本のアパレル業界のスタンスでした。そこにオリジナリティなんていうものはなく、決まりきった形のセーターしかなかった。
私が目指しているのは、イタリアの工場みたいに「新しいトレンドを生み出す会社」ですね。そうならない限りは、いずれ会社がダメになると、そのときに思いましたから。
そこから、佐藤さんの挑戦が始まったんですね。
そうですね。ただ、当時の日本では、独自のスタイルで自分のブランドを作って発表すると、圧力をかけられたのです。そのため、日本ではなくニューヨークでスタートすることにしました。新しい機械もない状態だったので、ここでも古い機械を改造して使っていましたね。
実は、日本の糸作りにおいてきれいな糸が作られるようになったのは、120年ほど前からになります。それ以前は、羊の年齢や毛の長さで分けることもなく一緒くたに使用していました。長い毛も短い毛もすべて混ぜて糸を作っていたので、原料としてはかなり雑なものだったのです。
ただ、その頃に使われていた機械は、粗悪な原料を用いても作れるほど丁寧な造りをしていました。今の機械は高速化・低コストにすることを重視した構造なので、特殊なものが作れません。独自の商品を作るには、古い機械が一番理想的な構造になっています。自分で機械を改造すれば、糸作りがより面白くなるのです。
.jpg?w=700&fm=webp)
この記事は会員限定です。
登録すると続きをお読みいただけます。
- 会員限定記事の閲覧、
音声読み上げ機能が利用可能 - お気に入り保存、
閲覧履歴表示が無制限 - 会員限定のイベント参加
- メールマガジン配信で
最新情報をGET