
ファッションをめぐる素材開発は目覚ましい進化を遂げ、様々な新素材も登場しているが、その一方で、伝統的な素材の生産方法にアプローチするような研究も存在する。
今回、取材した九州大学大学院の池永照美さんは、世界中で古くから人間の生活に根付いていた蚕糸をめぐる研究に取り組んでいる。蚕に繭を作らせない平面吐糸、セルロースと組み合わせた新たな素材開発など、伝統的な養蚕の形とは異なる多様なアプローチについてお聞きしました。
PROFILE|プロフィール
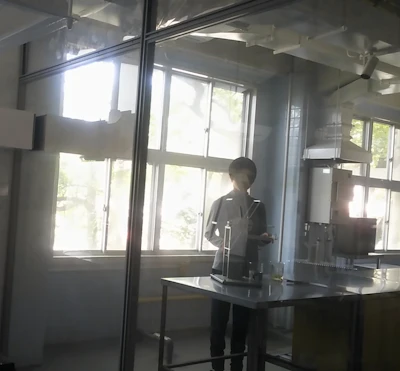
池永 照美/Ikenaga Terumi
シルクリサーチャー。修士(文学)。19世紀のフランス文学Madame Chrysanthème, Japoneries d'Automne, Pierre Lotiを服飾描写から読み解く中で、当時の日本とリヨンの絹を通した文化交流に、シルクの可能性を感じる。地元の伝統的工芸品、博多織の作り手と携わる中で、素材の大切さを実感し、現在は、九州大学大学院生物資源環境科学府家蚕遺伝子資源学分野博士後期課程に在籍する。800を有する蚕の系統の中から原種を中心にシルクの特性、個性を調査中。
繭を作らない「平面吐糸」
まず、蚕が繭を作らずに平面に糸を吐く「平面吐糸」をめぐる研究についてお聞きしていきます。これは蚕の研究全般で定番のアプ�ローチなのか、研究の背景や文脈を教えてください。
蚕が平面吐糸をするというのは、蚕に携わる人であればご存じの方が多いと思います。たとえば科学館や博物館で、団扇の枠に蚕に糸を吐かせるようなワークショップをするところもあるので。また、大学や研究者が平面吐糸をしてみることもあります。ただ実際には、いわゆる衣服用のシルクを作る時には、養蚕農家さんはいい繭をたくさん作り、たくさん売りたいので、平面吐糸をさせようとしません。産業として蚕を育てている方たちは絹糸にする繭を作りたいので、蚕によい繭をたくさん作ってもらいたいと思っているのではないかと思います。
この記事は会員限定です。
登録すると続きをお読みいただけます。
会員登録でできること
- 会員限定記事の閲覧、
音声読み上げ機能が利用可能 - お気に入り保存、
閲覧履歴表示が無制限 - 会員限定のイベント参加
- メールマガジン配信で
最新情報をGET
CONCEPT VIDEO
「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開
PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。
関連記事
RELATED ARTICLES
CONCEPT VIDEO
「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開
PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。
CONTACTお問い合わせフォーム
ご質問やご要望がございましたら、以下のフォームに詳細をご記入ください。















.png?w=400&fm=webp)
.jpg?w=400&fm=webp)


