【対談】貞包英之・林凌 消費社会とファッションはどこへ向かうのか 大量消費? エシカル? それとも、、?

私たちは日々消費をくりかえしつつ生きている。ファッションも、消費の一分野として大きな存在感を持っている。しかし、そもそも消費とは何をさすのだろうかと言われると私たちは言葉に詰まってしまうかもしれない。あまりにも日常的であるが故に、それを改めて語ることには難しさが残る。
そこで今回は、消費社会論を専門とする貞包英之教授(立教大学)と林凌氏(日本学術振興会特別研究員(PD))をお招きし、消費社会におけるファッションの位置付けと展望についてお話を伺った。
PROFILE|プロフィール
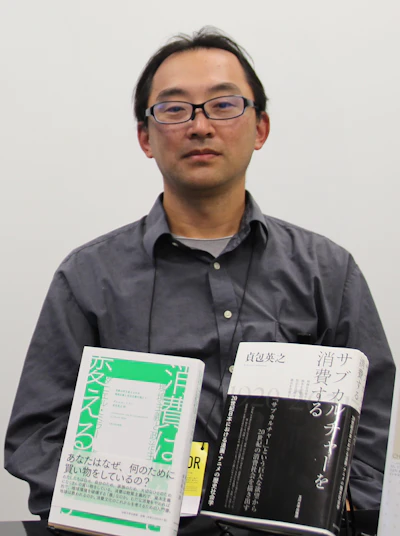
貞包英之
立教大学社会学部教授、専攻は社会学・消費社会論・歴史社会学、東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得満期退学。著書に『地方都市を考える 「消費社会」の先端から』(2015年、花伝社)、『消費は誘惑する:一八、一九世紀日本の消費の歴史社会学』(2015年、青土社)、『サブカルチャーを消費する:20世紀日本における漫画・アニメの歴史社会学』(2021年、玉川大学出版部)、『消費社会を問いなおす』(2023年、筑摩書房)など。
PROFILE|プロフィール
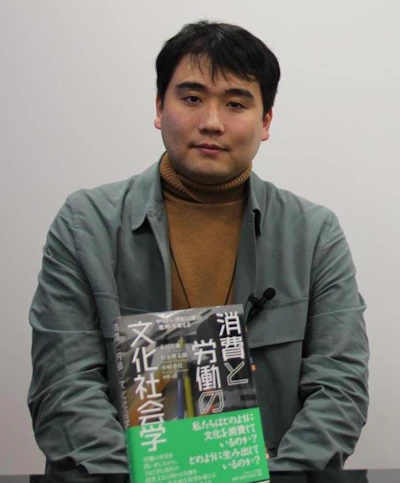
林凌
日本学術振興会特別研究員(PD)、専門は消費社会論、思想史、流通史。徳島県出身。東京大学大学院学際情報学府博士満期退学、博士(社会情報学)。近年の業績として、『〈消費者〉の誕生――近代日本における消費者主権の系譜と新自由主義』(単著、以文社、2023年5月刊行予定)、『労働と消費の文化社会学――やりがい搾取以降の「批判」を考える』(分担執筆、ナカニシヤ出版、2023年1月刊行)などがある。
消費で社会を考えること
お二人のご研究内容について簡単に教えてください。
貞包私は消費の歴史と現代の具体的な事例について社会学的に考えてきました。たしかに消費は社会学ではよく使われるキーワードの1つです。たとえば、文化現象を研究する際に頻繁に言及され、消費されるコンテンツとそれを消費する人々の階層との結びつきなどがさかんに指摘されています。
このような分析はそれ自体として価値があるのでしょうが、消費を固有の問題として扱っているようにはみえません。たとえばある商品にかんして、どのようにお金を手に入れて、何のために買っているのかを主題的に分析する研究は社会学では少ないように感じます。そこで私は、消費がいかなる人にいかなる条件で可能になり、それがどのように社会を動かしてきたのかについて歴史的に研究してきました。最近では、漫画やアニメなどのコンテンツの消費を例とした本を書いています。
この記事は会員限定です。
登録すると続きをお読みいただけます。
会員登録でできること
- 会員限定記事の閲覧、
音声読み上げ機能が利用可能 - お気に入り保存、
閲覧履歴表示が無制限 - 会員限定のイベント参加
- メールマガジン配信で
最新情報をGET
CONCEPT VIDEO
「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開
PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。
関連記事
RELATED ARTICLES
CONCEPT VIDEO
「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開
PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。
CONTACTお問い合わせフォーム
ご質問やご要望がございましたら、以下のフォームに詳細をご記入ください。














.png?w=400&fm=webp)




