【リレーコラム】ファッション研究者、就活の服装に悩む(五十棲亘)

PROFILE|プロフィール
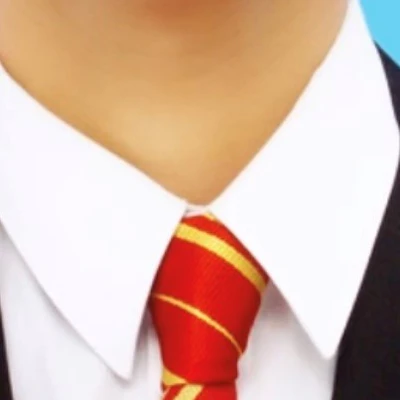
五十棲亘
京都服飾文化研究財団 アシスタント・キュレーター。専門はファッション文化論、表象文化論。とりわけ戦後日本におけるファッションデザインに対する批評の研究。主な論考に「Y2Kは現代語か─ファッションリバイバルとアーカイブファッションの身体」『ユリイカ 2022年8月号 特集=現代語の世界』(青土社)、共著に『クリティカル・ワード ファッションスタディーズ 私と社会と衣服の関係』(フィルムアート社)がある。
researchmap
ファッション研究者として、就職活動という事象に関心をもってきた方だと思う。画一的な服装や髪型や髪色、近年は女性のみならず男性においても「清潔感」の惹句とともに推奨される化粧。あるいは、着席の仕方やおじぎ等の振る舞い、あるいは慇懃無礼といえるほどの丁寧語などなど。とりわけ、過度のハイヒール着用や選考におけるルッキズムといった近年のトピックは(1)、ファッション研究の観点からも看過することはできない。
このように、メディアでは何らかの形で装いや振る舞いの視点から就職活動への意見が日常的に交わされる。そして、就職活動とファッションの関係性において、スーツに対する服装の規範は私自身も多くのことを考えさせられた問題だ。
スーツは、服飾史やファッション研究において極めて重要な研究対象である。なぜなら、スーツの歴史は単なる衣服の形態の変��遷だけでなく、近代化の過程とともにスーツに付与されてきた様々なアイデンティティをめぐる歴史でもあるからだ(2)。
スーツとは、ユニフォームとして何らかの属性に押し込めようとする運動と、そこから抵抗するように生ずる差異化の運動が拮抗し合う言説の構築物である。そして、田中里尚が『リクルートスーツの社会史』で丹念に分析しているように、そうした言説の構築物としてのスーツの側面が明らかになる事例が就職活動におけるリクルートスーツの問題である(3)。
この記事は会員限定です。
登録すると続きをお読みいただけます。
会員登録でできること
- 会員限定記事の閲覧、
音声読み上げ機能が利用可能 - お気に入り保存、
閲覧履歴表示が無制限 - 会員限定のイベント参加
- メールマガジン配信で
最新情報をGET
CONCEPT VIDEO
「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開
PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。
関連記事
RELATED ARTICLES
CONCEPT VIDEO
「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開
PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。
CONTACTお問い合わせフォーム
ご質問やご要望がございましたら、以下のフォームに詳細をご記入ください。








.jpg?w=400&fm=webp)

.jpeg?w=400&fm=webp)





.png?w=400&fm=webp)
.jpg?w=400&fm=webp)

